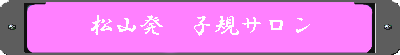 |
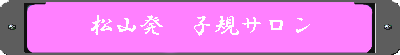 |
| 17 | 子規さん俳句鑑賞(続) 令和5年1月以降 |
|
|
|||||||||
令和五年月一月 「水仙も 処を得たり 庭の隅 子規 」 子規記念博物館(総館長 竹田美喜氏)監修の子規さんの令和五年一月句は「水仙も 処を得たり 庭の隅 子規 」です。 『子規全集』第三巻 俳句三 123頁「俳句稿」(明治三十年 冬)と第十五巻 俳句会稿 609頁(明治三十年)に掲載されている。季語は「水仙」(冬)である。 この句の詞書に「新宅祝」とある。明治30年には、高浜虚子が結婚を機に日暮里村に新居を設けたので、句会の題に「新宅祝」とされたのであろう。 虚子の新宅のイメージが湧かないが、寒気の中でも凛と咲く水仙を通して、虚子の門出を祝う子規の気持ちが伝わってくる。 虚子の妻は、河東碧梧桐の「思われ女<ひと>」であったが・・・漱石の「こころ」をイメージする。恋はいつの時代でも苦しいものである。 同句会での「交りは安火<あんか>を贈り祝ひけり」(河東碧梧桐)を虚子が採っている。微妙な友情の世界であろうか。 他の参加者の句も披露しておこう。 新宅を 賀すべく冬至 梅一枝 愚哉 新宅に 春待つ君を なつかしむ 繞石 新宅の 庭に咲きけり 玉椿 春風庵 子規さんにあやかって一句 元旦の時宗宝厳寺にて 「子を抱く庵主の正座 日向ぼこ 子規もどき」 |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 令和五年月二月 「公園の 梅か香くはる 風のむき 子規 」 | |||||||||
子規記念博物館(総館長 竹田美喜氏)監修の子規さんの令和五年二月句は「公園の梅か香くはる風のむき 子規 」です。 子規「ノート」に明治22年4月5日付で記入されている。季語は「梅が香」(春)である。この「ノート」であるが、第一高等学校在学中、受講ノートの余白に書いたもので、俳句のほかに和歌、漢詩、小説など多岐に渡っている。 4月5日当日は、6日間の水戸旅行の途中で、梅の名所「偕楽園」を訪ねている。メモでなく受講ノート持参の旅行とは、ほほえましい。 (この項は、子規記念博物館 野口稔里学芸員の解説に拠る。) 月初に当月の子規さん句を確認に子規博に出かける。子規博に「仕掛け」があって、正面玄関の懸垂幕で道行く人にも「子規さんの句」がわかるようにしている。 懸垂幕を眺めて、この句を「公園の梅か 香ぐ 春風の向き 子規」と読んだが、梅と春風との「季重なり」である。凡句だなと感じた。 「公園の 梅が香配る 風の向き 子規」と分るまで、結構な時間がかかった。俳句とは難しい。いやはや。 句意は、公園(偕楽園)の広い園内を歩いていると、梅の香りが風に運ばれてくる。時には鼻につき、時にはほのかに香りが漂う。香りの微妙な変化と風の向きの感覚が、子規さんの鋭い観察眼といえよう。 梅の季節に、学生時代から偕楽園には何回か訪ねたが、水戸烈公や水戸学の歴史に視点があり、折角の梅の香まで味あう余裕はなかった。残念、残念。 子規さんにあやかって一句 「梅の香や 水戸烈公の 潔さ 子規もどき」 |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 令和五年月三月 「大仏のうつらうつらと春日哉 子規 」 子規記念博物館(総館長 竹田美喜氏)監修の子規さんの令和五年三月句は「大仏の うつらうつらと 春日哉 子規 」です。 『子規全集』第一巻 俳句一 193頁「寒山落木 巻二」(明治二十六年 春)と第十三巻 小説 紀行 528頁「鎌倉一見の記」(明治二十六年)、第二十一巻 草稿 ノート 9頁「寒山落木別巻」に掲載されている。季語は「春日」(春)である。 「寒山落木別巻」では「大仏のうつらうつらと春日哉」であるが、「寒山落木 巻二」「鎌倉一見の記」では「大仏のうつらうつらと春日かな」である。研究は別として、メモ でなく公表(出版)された作品の句(この場合は「大仏のうつらうつらと春日かな」)を用いるべきであろう。 春のうららかな日に、訪れた(鎌倉)大仏の穏やかな表情はうつらうつらと微睡んでいるようだ。眺める観光客も同様だ。鎌倉市民も、鎌倉も、」ゆったりと春日を楽しんでいる。子規さんも東京への帰途、うつらうつらと微睡んで汽車の旅を楽しんでいる。 この句は「鎌倉一見の記」(明治二十六年)でエッセイとしてまとめているように、保養中の日本新聞社社長「陸羯南」を訪ねた旅の中で詠まれた。 蛙鳴く 水田の底の 底あかり 鶯や おもて通りは 馬の鈴 鶯や 左の耳は 馬の鈴 岡あれば 宮宮あれば 梅の花 家ひとつ 梅五六本 こゝもこゝも 旅なれば 春なればこの 朝ぼらけ 陽炎や 小松の中の 古すゝき 春風や 起きも直らぬ 磯馴松(そなれまつ) 銀杏とは どちらが古き 梅の花 陽炎と なるやへり行く 古柱 鎌倉は 井あり梅あり 星月夜 歌にせん 何山彼山 春の風 大仏の うつらうつらと 春日かな 梅が香に むせてこぼるゝ 涙かな 明治26年当時の鎌倉の春の情景が浮かんでくるようだ。 子規さんは「大仏」が気に入ったのか、前句で大仏を詠んだ句が65句ある。(『子規俳句索引』子規博編) 「鎌倉一見の記」は「泣く泣く鎌倉を去りて再び帰る俗界の中に筆を採りて鎌倉一見の記とはなしぬ」で結んでいる。 子規さんにあやかって一句 妻の七回忌を父子三人で送る 「七回忌 うつらうつらと 春暮れる 子規もどき」 道後関所番 |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 令和五年四月 「夜桜や 露ちりかゝる 辻行燈 子規 」 子規記念博物館(総館長 竹田美喜氏)監修の子規さんの令和五年四月句は「夜桜や 露ちりかゝる 辻行燈 子規 」です。 『子規全集』第一巻 俳句一 57頁「寒山落木 巻一」(明治二十五年 春)と第十八巻 書簡一 265頁「五百木良三宛明治二十五年二月二十一日カである。 子規の名を伏せて鑑賞するとすれば「辻行燈」から明治初期、場所を上野とすると、吉原の帰途か、上野公園での逢引きを連想し、艶っぽい句と感じるのは、わが性の因果か。 ほのかな辻行燈の辺り、桜の花びらが露を含んで散っていく。連れは女性、それも玄人筋だろう。夜も更けてくる・・・・・・ 70年近い昔、下宿先のお嬢さんと洗足池公園の夜桜を愛で散策したことがあるが、「露ちりかかる」という風情は浮かばない。 露伴か、紅葉か、それとも歌舞伎の一場面か。ここで種明かしがあって「子規作」という。 この句は、「燈火十二ヶ月」と題した十二句の中の一句で、子規の詩湯していたランプの笠に書かれている。 この「燈火十二ヶ月」の句を詠んだ時、大学の試験勉強中であったが、俳句が一句、一句とと浮かび、試験勉強をお預けして俳句つくりに熱中して・・その結果、この時の試験?は当然無残な結界に終わる。 子規らしい性向ではあるが、松山藩の下級武士の総領としての行動としては同意できかねる。 次に「燈火十二ヶ月」の十二句を披露する。 一月 袴きて 火ともす庵や 花の春 二月 紅梅の 雪洞遠き 長廊下 三月 夜桜や 露ちりかゝる 辻行燈 四月 行燈の 丁字よあすは 発松魚 五月 おそろしや 闇にみだるヽ 鵜の篝 六月 あんどんは 客の書きけり 一夜酒 七月 燈篭の 火に音たてヽ 秋の風 八月 神に灯を あげて戻れば 鹿の声 九月 灯ともせば 灯に力なし 秋のくれ 十月 しぐるヽや ともしにはねる やねのもり 十一月 灯の青う すいて奥あり 藪の雪 十二月 いにしへは くらしらんぷの 煤払 子規博学芸員野口稔里さんの解説を付記しておきたい。 「夜、辻行燈のやわらかな明かりが桜を照らしています。盛りを迎えたそばから散っていく花びらとともに散りかかる露は、より儚さをかきたてます。」 子規さんにあやかって一句 「夜桜や 指のブリッジ LD燈 子規もどき」 |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 令和五年五月 「とげ赤し 葉赤し 薔薇の枝若し 子規 」 子規記念博物館(総館長 竹田美喜氏)監修の子規さんの令和五年五月句は「とげ赤し 葉赤し 薔薇の枝若し 子規 」です。 『子規全集』第二巻 俳句二 507頁「寒山落木 巻五」(明治二十九年 夏)に掲載されている。 「あかし」「あかし」「わかし」と繰り返すリズム感は、100年前の文学青年のリズム感としては瑞々しい限りである。もっとも俳句としては如何なるものか。 明治29年といえば、子規の脊椎カリエスは進行し子規庵に閉じ籠っており、時に杖をついて庭を歩くことで自然に接することが出来る機会であったのであろう。 そこで、棘も、葉も赤い、そして枝も若々しい薔薇の若木か、今春枝分かれした枝と相対し、若々しい生命の息吹に感嘆したのであろう。 わが庭の薔薇も只今現在同様であり、一輪だけ咲いている。朝夕の主人の出入りを出迎え、見送ってくれる。子規の写生句の凄さを痛感している。 |
|||||||||
| 子規さんにあやかって一句 「薔薇一花 独居の庭を睥睨す 子規もどき」 |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 令和五年六月 「四阿に 日の影動く 若楓 子規 」 子規記念博物館(総館長 竹田美喜氏)監修の子規さんの令和五年六月句は「四阿に日の影動く若楓 子規 」です。 『子規全集』第三巻 俳句三 399頁「俳句稿以後」(明治三十四年 夏)に掲載されている。 前書き「若楓」で四句作っている。 四阿に 日の影動く 若楓 寺を見て 茶のもてなしや 若楓 若楓 案内の小僧 可愛げに 若楓 仮名巧なる 写し物 明治34年と云えば子規の最晩年で寝たきりの日常である。想像した風景を詠んだものだが、鎌倉の寺か、江戸の寺か、伊予松山の寺か、考証は難しい。道後周辺だと初代松山藩主を弔う祝谷山「常信寺」の雰囲気だが、子規は訪ねていない。 寺参りの途中で、広い境内の片隅にある四阿に腰を下ろした。周りの景色を眺めると、青々と茂る若楓の葉影と木漏れ日とが揺れ動いている。体の汗も気にならなくなった。さて、本堂にお詣りしようかな。・・・・・ 子規博の解説によると、この句は明治34年7月7日発行の新聞『日本』に発表された。 同紙では、同じ若楓を題に取り、様々な俳人が句を詠んでいる。 水落(みずおち)露(ろ)石(せき)(子規派の大阪満月会俳人)の「四阿の 紅提灯や 若楓」のように、新緑と紅提灯の色のコントラストに美しさを見出した句など、個性豊かな句が並びます |
|||||||||
| 子規さんにあやかって一句 「綴葺(しころぶき)の 本堂を背に 若楓 子規もどき」 令和五年七月 「いろいろの 夢見て夏の一夜哉 子規 」 子規記念博物館(総館長 竹田美喜氏)監修の子規さんの令和五年七月句は「いろいろの 夢見て夏の一夜哉 子規 」です。 『子規全集』第三巻 俳句三 151頁「俳句稿」(明治三十一年 夏)に掲載されている。 詞書「第十二議会解散」がある。 第十二回帝国議会は明治31年5月14日から同年6月10日まで開催された。 1か月にも満たない短期議会である。もっとも、この議会での審議内容についてはまったく知らない。 子規は『日本』の記者であり、ジャーナリストとして当然帝国議会の動きには注目していたと思われるが、詳細は不明である。 「いろいろの夢」の正体を知りたいものである。 詞書「第十二議会解散」を無視すると、恋の歌とも、老いの歌ともとれるが、詞書を前提にすると、議会の審議内容が与野党で激しい議論となるが、政党の妥協と駆け引きで、子規が関心をもった外交や国内対策のあるものが承認され、またされ、廃案になって いく。 短い夏の夜に見る夢のように、うたかたの一場として、儚く消え去っていく。もっと国会論議を尽くさねばと痛感したのではあるまいか。 「時事俳句」の範疇に入るのだろうか。俳句としての、そこまで深く監守すべきかどうか。 子規さんにあやかって今次国会の「時事俳句」を詠んでみたい。 「いろいろの 後付けマイナ かたつむり 子規もどき」] 漢字、ひらがな、カタカナを多用してみた失敗作だ。いやはや。 令和五年八月 「君来ばと 西瓜抱えて 待つ夜かな 子規 」 子規記念博物館(総館長 竹田美喜氏)監修の子規さんの令和五年八月句は「君来ばと 西瓜抱えて 待つ夜かな 子規 」です。 『子規全集』第二巻 俳句二 123頁「寒山落木 巻三」(明治二十七年 秋)に掲載されている。 季語は「西瓜 秋」である。 西瓜は感覚的にも夏を代表する果物であるが、俳句の季語は「秋」である。 手元にある山本健吉編の「歳時記」でも季節感のズレのコメントはない。 句自体は「君が来たならば一緒に食べようと、西瓜を抱えて待っている夜です。」と平明である。気になるのは「君は誰か」ということだろう。 はっきりしているのは妙齢の女性ではなく、気に置けない彼奴であろう。河東碧梧桐か高浜虚子であろうか。 この句が詠まれた明治二七年の夏と云えば、体調もよく、千住方面、王子、川崎大師、千葉方面に小旅行をし、紀行文を書いている。 また郷里松山の後輩である碧梧桐と虚子が、この年、第三高等学校から第二高等学校に転学したが、共に退学し、東京に居を構えている。 子規にとっては心配であったろう。 子規博の学芸員 野口稔里さんのコメントに拠れば、子規は西瓜が大好物であった由。 随筆『松蘿玉液』では、「甜瓜(まくわうり)西瓜(すいか)ひなびたれど誠あり。捨て難し」、つまり「甜瓜や西瓜は田舎っぽいけれど誠実な印象で捨てがたい果物である」と評している。 子規さんにあやかって一句 「終戦の 玉音放送 西瓜食う 子規もどき」 昭和20年8月15日、祖母、父母と「離れ」で、玉音放送を聞いた。 小学生4年生の悪ガキでも日本が負けたことはわかった。 そして、井戸から冷えた西瓜を食べながら、家族で今後の不安を語った。 「季重ね」であるが、私にとって、玉音放送と西瓜は80年の年月は流れたが忘れることのできないワンショットである。 令和五年九月 「天の川 すこしねぢれて 星が飛ぶ 子規 」 子規記念博物館(総館長 竹田美喜氏)監修の子規さんの令和五年九月句は「天の川 すこしねぢれて 星が飛ぶ 子規」です。 『子規全集』第二巻 俳句二 539頁「寒山落木 巻五」(明治二十九年 秋)、第十五巻 俳句会稿 453頁(明治二十九年)、第十九巻 書簡 190頁 (明治三十年)に掲載されている。 第十五巻、第十九巻では「令和五年九月 「天の川 少しねぢれて 星が飛ぶ 子規 」となっている。 天の川がすこしねぢれているのか、少しねぢれて星が飛ぶのか・・・はて如何なものか。 天空に天の川がねぢれて広がっている。その天空から長い尾を引いて星が流れる。おそらく実景(写生)だろう。誰しも経験したことのあるドラマである。 子規は「高濱清」宛書簡(明治三十年八月十一日付)で「天の川」を連句している。 三尺の 幅とこそ見れ 天の川 行ゝて 左になりぬ 天の川 海原や 空を花るゝ 天の川 野の空や ものをはなれて 天の川 膳所越えて 湖水に落ぬ 天の川 川上ハ 東と見えて 天の川 立てかけし 杉の丸太や 天の川 北國の 庇ハ長し 天の川 天の川 少しねぢれて 星が飛ぶ 天の川 山なき国の 真上哉 複道や 銀河に近き 灯の通ひ天の川 十一句あるが、どれも秀句とは思えない。現代の宗匠は変な理屈をつけてランク付けするのだろうヵ。 ところで本句は明治二十九年八月に開催された句会で、「天の川」のお題として詠まれたものである。 高得点句 「帆柱の 上に横ふ 天の川 把栗」 「人去て 瀧とうとうと 天の川 蒼苔」 「妹山と 背山のなかを 天の川 墨水」 子規さんにあやって一句 「白ロシアに 流血の跡 天の川 子規もどき」 |
|||||||||
川上ハ 東と見えて 天の川 立てかけし 杉の丸太や 天の川 北國の 庇ハ長し 天の川 天の川 少しねぢれて 星が飛ぶ 天の川 山なき国の 真上哉 複道や 銀河に近き 灯の通ひ天の川 令和五年十月 「つぶつぶと 丸む力や 露の玉 子規」 子規記念博物館(総館長 竹田美喜氏)監修の子規さんの令和五年十月句は「つぶつぶと 丸む力や 露の玉 子規」です。 『子規全集』第一巻 俳句一 110頁「寒山落木 巻一」(明治二十五年 秋)に掲載されている。季語は「露」(秋)である。 当時子規は「一題百句」として「鹿」や「笠」を題にしており、「露」も同類である。 ほろほろと 露の玉ちる 夕哉 灯のちらり ちらり通るや 露の中 などが詠まれている。 子規25歳の句であるが、一読して、今日の「俳句甲子園」に提出すれば、高校生らしい理屈っぽい句として高く評価されるのではあるまいか。 説明句に近いが、明治25年当時では科学的な説明に驚いたのではあるまいか。 子規博物館担当者の解説 「本句の季語「露」とは、空気中の水蒸気が冷たい物体の表面に凝結して水滴になったものです。日が昇ると瞬く間に乾いてしまったり、風が吹けば落ちてしまったりすることから、儚いものや哀れなもののたとえに用いられます。 しかし本句では、むしろその造形の不可思議な美しさと、それを実現させる「丸む力」、つまり表面張力に着目することで、従来の露のイメージにとらわれない写実的な句となっています。」 恐れ入りました。理科の嫌いな子規さんも驚いていることでしょう。 「寒山落木 巻三」(49頁)では 「つぶつぶと 芽をふいて居る 老木哉」と詠んでいる。 米寿を迎えた老生には、この句の方が「生・老・病・死」の深い叡智を感じさせる句と思えるのだが・・・・・ 子規さんにあやかって一句 「露の玉 移し遊ぶや 老いふたり 子規もどき」 令和五年十一月 「二つ三つ 石ころげたる 枯野かな 子規 」 子規記念博物館(総館長 竹田美喜氏)監修の子規さんの令和五年十一月句は「二つ三つ 石ころげたる 枯野かな 子規」です。。 『子規全集』第三巻 俳句三 308頁「俳句稿」(明治三十二年 冬)と第十五巻 俳句会稿 709頁「俳句稿」(明治三十二年 )に掲載されている。 季語は「枯野」(冬)である。 子規晩年の作である。 「枯野」といえば、芭蕉も晩年旅の途中で病に倒れ「旅に病で 夢は枯野を 駆け廻る」なる有名な句を残した。 病臥にあった子規は、芭蕉の句を念頭に詠んだのであろう。 写生句としては疑問に感じる。枯野、石ころ、二つ三つの取り合わせは如何なものか。 「二つ三つ 岩不動たる 枯野かな」となるとブロンテの『嵐が丘』を想起する。 「二つ三つ 石重ねたる 枯野かな」となると関ヶ原を想起する。 多くの俳人の鑑賞と異にするが、子規は夢と現実の狭間で、枯野を彷徨う芭蕉や芭蕉を慕う門人をイメージしたのではあるまいか。。 芭蕉、蕪村そして子規なのかもしれない。今その石は「ころげたる」であり、静止は許されない。「枯野」の寂寥感は消えて「軽やかさ」すら感じる。 子規さんにあやかって一句 「二つ三つ 石ころげたる 遍路哉 子規もどき」 」 令和五年十二月 「餅搗て 春待顔の 子猫哉 子規 」 子規記念博物館(総館長 竹田美喜氏)監修の子規さんの令和五年十二月句は「餅ついて 春待顔の 子猫かな 子規 」です。 『子規全集』第三巻 俳句三 306頁「俳句稿」(明治三十二年 冬)と第十五巻 俳句会稿 700頁「句稿」(明治三十二年 )に掲載されている。 季語は「餅搗」(冬)である。 「俳句会稿」では「餅搗て 春待顔の 子猫哉 子規」と漢字を多用している。 幼少期のわが家は、使用人も多く、早朝から大釜で餅米を焚き蒸して、家族・使用人総出で昼まで餅づくりであった。 神仏に供える鏡餅類、お雑煮の丸餅、お茶請けの餡餅、かき餅用の角餅(菱餅)などなどであった。 わが家に猫はいなかったが、犬は土間で人の出入りをじっと眺めていたようだ。 西洋犬だったから、餅には興味がなかったのかもしれない。もっとも犬は餅が苦手であった。 子規の見た餅つきの光景は、石臼と、杵つきの男と、家族数人であろう。子規晩年の作である。 人間が師走だけにせわしなく動き回っているのに、小さな猫が座っているのか、寝転んでいるのか、春待顔でのんびりと眺めている。 皮相的に見れば、春待顔の子猫は子規さんのことかもしれない。あるいは、子猫を抱いて蒲団の上の座っている子規さんを想像してみてはいかがであろう。 この句は明治32年12月10日の句会の席題「餅搗」で詠まれたものである。 参加者の句を並べてみました。正月気分になりましたでしょうか・・・ 餅搗の 手伝顔や 里帰り 碧梧桐 三臼目を 鏡餅とは なしにけり 虚子 餅搗の 既に来て居る 鄰哉 鳴雪 餅搗や 早く起きたる 五六人 墨水 子規さんにあやかって一句 戦後の混乱期にて 「餅搗て 春待顔の 施設の子 子規もどき」 令和六年一月 「春またず 年もをしまず 寒の梅 子規 」 子規記念博物館(総館長 竹田美喜氏)監修の子規さんの令和六年一月句は「春またず 年もをしまず 寒の梅 子規」です。 『子規全集』第三巻 俳句三 505頁「寒山落木 拾遺」(明治二十六年 冬)に掲載されている。 季語は「寒の梅」(冬)である。 この句を漢字に置き換えてみる。 「春待たず 年も惜しまず 寒の梅」となる。 「春待たず」(冬)、「年も惜しまず<師走>」(冬)、「寒の梅」(冬)とすると冬の三連荘である。 これを以て、佳句と云われても困る。子規だから許されることではあるまい。 句は「春を待たず、年明けも待たず、寒中に毅然として梅が咲いている」という情景の説明句に過ぎない。それ以上でも、それ以下でもあるまい。凡句である。 子規さんにあやかっての「子規もどき句」も、今回はご遠慮させていただこう。 令和六年二月「思い出し思い出しふる春の雪」 子規記念博物館(総館長 竹田美喜氏)監修の子規さんの令和六年二月句は「思い出し 思い出しふる 春の雪 子規」です。 『子規全集』第三巻 俳句三 532頁「寒山落木 拾遺」(明治二十六年)と第十八巻 書簡一 414頁に掲載されている。季語は「春の雪」で(春)である。 今日でも2月中旬の「椿さんの祭礼」が終わってから暖かくなるといわれており、明治期には3月でも積雪があったのだろう。 幼時には雪だるまや雪合戦を楽しんだものだ。 書簡の宛名は「五百木良三」(瓢亭)宛で明治26年3月1日付である。瓢亭は松山出身で俳句仲間である。 この句の主役が春の雪とすると「(冬を)思ひ出し 思ひ出し降る 春の雪」の5・7・5の句となり、 作者(子規)の心情を強調とすれば「思ひ出し 思ひ出し 古る春の雪」だと、5・5・7の句となる。 明治25年秋の子規句に「思ひ出し 思い出しひく 鳴子哉」がある。この句の場合、鳴子が主役ではなく、作者(子規)の心情(行為)が主役ではなかろうか。 俳人にお教えを受けたい。 子規博の公式コメントを引用する。 「子規は、病気の容体や訪問者のない退屈さ、養生せよと云う医者に対して、自分が働かなければ立ちいかない一家の経済状況など、不満を述べています。 一方で、仲間たちと刊行する俳句雑誌の進捗や、瓢亭への投句依頼、与謝蕪村に倣って十二ヶ月の俳句を詠んだことなどが書かれています。」 子規さんにあやかっての「子規もどき句」 「思い出し 思い出しふる 除夜の雨 子規もどき」 令和六年三月「のどかさや つゝいて見たる 蟹の穴 子規」 子規記念博物館(総館長 竹田美喜氏)監修の子規さんの令和六年三月句は「 子規」です。 『子規全集』第三巻 俳句三 319頁「俳句稿」(明治三十三年)と第十五巻 俳句会稿 735頁(明治三十三年)に掲載されている。季語は「蟹」で(春)である。 句意は「穏やかに時間が流れる春の日に、所在なく蟹の穴をつついていた」という実景であろう。 松山の梅津寺の閑散とした浜辺で、穴を見つけてはつついていた幼い日の記憶がよみがえる。子規さんの情景も、三津から高浜にかけての海浜の思い出かもしれない。 この句は明治33年2月11日の子規庵での句会で「蟹(春)」がお題であった。この句会には19人集まり盛大であった。 竹 子 秋 蘭 蟹眠る 砂や磯邉の 春日和 東洋城 古き江の 蘆の芽ぐみや 蟹の泡 大 夢 山吹や 蟹のかくるゝ なべの尻 芹 村 ぬくき日を 泡ふく蟹や 石の上 虹 原 石とれば 小蟹群れけり 春の磯 牛 伴 繞 石 蘆の芽や 蟹歩みよる 池の水 四方太 春の水 蟹の穴にも 流れけり 抱 琴 三 充 蟹ばかり 追ふてゐる子の 汐干哉藜 孤 鴈 舟橋や 蟹のうごめく 蘆の角 藜 杖 麦 人 春の水 蟹の出て居る 處哉 碧梧桐 人を見て 蟹 足の 汐干哉 鳴 球 ぬくき日を 蟹とる子供の 臀哉 格 堂 永き日や 蟹釣って居る 村の馬鹿 三 子 干る汐に のがれかしこき 小蟹哉 子 規 のどかさや つゝいて見たる 蟹の穴 <俳句会稿百四十九> 子規博のコメントを付記する。 「子規は、蟹そのものではなく、蟹の穴に焦点をあてています。蟹がどこにいるのか判然としませんが、蟹の穴を通して、蟹が人前に姿を見せて活発に動き始める春の到来を感じさせます。」 そんな深遠なたくらみがあったとは・・・まいった、参った。 子規さんにあやかっての「もどき句」 妻の八回忌 「のどかさや 写真を前に まず献杯 子規もどき」 令和六年四月「大仏のよごれた顔や山桜 子規」 子規記念博物館(総館長 竹田美喜氏)監修の子規さんの令和六年四月句は「大仏のよごれた顔や山桜 子規」です。 『子規全集』第十五巻 俳句会稿 470頁に掲載されている。季語は「山桜」で(春)である。 鎌倉の大仏を詠んだ句である。大仏の汚れた顔と武家政治の嚆矢である鎌倉幕府と思い重ねて歴史の流れ、時間の流れを詠嘆を込めて詠んだのであろうか。13世紀の中葉には完工しているので、一遍上人一行も大仏を拝観したのであろうか。 何度もこの地を訪れたが、現在は大仏の胴内にも入れるので、子供にも、外国人にも好評な観光施設になっている。これも又、時代の流れというべきk。 この句会は、明治29年春に開催された。表題は「日半日」、参会者は、紅葉、奇峰、瓢亭、虚子、碧梧桐、子規である。 子規は大仏を題に四句詠んでいる。 春 大仏のよごれた顔や山桜 2点(虚子 碧梧桐) 夏 大仏の頭吹くなり青嵐 秋 大仏の夕影長き刈田哉 1点(紅葉) 冬 倉仮に大仏見ゆる寒さ哉 碧梧桐 大仏を写真に取るや春の山 3点 虚 子 大仏に頭の上や星月夜 2点 子規さんにあやかっての「子規もどき句」 小学校の友と道後公園にて 「皇国の 擦れたる碑や 桜散る 子規もどき」 令和六年五月「うれしさは 旅より戻る 若葉哉 子規」 子規記念博物館(総館長 竹田美喜氏)監修の子規さんの令和六年五月句は「うれしさは 旅より戻る 若葉哉 子規」です。 『子規全集』第二巻 寒山落木 巻三 明治二十七年夏(75頁)に掲載されている。季語は「若葉」で(夏)である。 子規は旅好きな「歩く人」でもあったが、明治27年当時の旅は近郊の上野や王子権現への散策や諏訪明神参詣などであるが、特定は出来ない。 桜の後の新緑から深緑へ、山野の、大自然の変化は凄まじい。旅の始めと終わりの変容に気持ちは高揚する。旅からの帰り道の充実感を歌い上げている。人生賛歌である。 鳩寿を控えて、眼前の里山の新緑を眺めていると人生の青春を感じ、深緑で人生の朱夏を感じ、紅葉と秋空を前にて人生の白秋を素直に感じる。子規は20代後半であり、人生の深みはわかるまいが、この年配になってくると、旅そのものが人生になってくる。まさに人生は旅である。 子規さんにあやかっての「子規もどき句」 「うれしさは 墓参に戻る 青葉かな 子規もどき」 |